「活性酸素」と聞くと何を思い浮かべるでしょう?
「体に悪そう!」「フリーラジカル!」などとイメージできるのではないでしょうか。ところが、活性酸素は私たちの体になくてはならない存在なのです。
活性酸素は不安定な物質で、ほかの物質から電子を搾取して安定を得ようとします。しかし、取られた側は別の物質から……と負の連鎖が続いてしまっているのが問題。
その問題を解決するヒントをまとめていこうと思います。運動を好きな人はぜひご覧ください。

活性酸素とは?

酸素を使って生活している生物は、生きるためのエネルギーを作るためにミトコンドリアが酸素を消費して代謝を行なっています。
その過程で生まれるのが「活性酸素(ROS)」と呼ばれるもので、生命の維持に欠かせないものである一方で、身体の抗酸化力を上回ってしまった時に『酸化ストレス』という悪影響を及ぼします。
この酸化ストレスが慢性化すると体を蝕みはじめ、心血管疾患・がんなどの病気、DNAにもダメージを与えるため身体が炎症を起こし老化が進行する可能性が示されています。よって、抗酸化力を増やしておいた方がいいわけですね。
激しい運動は活性酸素を増やす原因!

運動による酸素摂取量は安静時の10〜15倍と言われており、活性酸素の生成量は爆発的に増えることが示されています。
しかし、オーバートレーニングのように過度な運動をしない限りは、むしろ抗酸化能力を高め、健康に良い効果が繰り返し確認されております。運動好きな人におすすめです。
激しい運動とは?どのくらいの強度?
基本的に、運動の強度が上がれば上がるほど活性酸素の量は増えるものの、個人の状態に大きく左右されるため酸化ストレスがどのくらいの運動により悪影響を与えるかは不明確です。
ゆえに、明確な基準はないのですが、最大酸素摂取量の50%以下であれば抗酸化作用を上回ることはないことが示されています。
さらに、一部の研究では、運動強度と酸化ストレスに関係はないと報告されていることからも、コンセンサスはないといえるでしょう。
なので、現状では「オーバートレーニング症候群のような症状が出るほど運動をしない」というのが、ひとつの目安になるのではないでしょうか。
適度な運動習慣の目安
適切な運動については、厚生労働省が推進している「健康づくりのための身体活動基準2013」に基づいて考えてみたいと思います。
結論からいえば、18〜64歳の人は、
- 強度3メッツ以上の身体活動を週に23メッツ時
- 強度3メッツ以上の運動を週に4メッツ時
となっており、具体的には、
- 歩行以上の強度を毎日60分以上
- 息が弾み汗をかく程度の運動を毎週60分ほど
となっております。
WHOの基準からは少し多め、2016年のメタ解析からはそこそこ少なめな基準となってますね。
活性酸素を増やさないための5つの生活習慣!

上記でも説明した通り、総活性酸素量が身体の抗酸化力を上回ることがない限りは有害な影響があるわけではないのですが、酸化ストレスを減らす可能性があるTipsを5つにまとめていきます。
ほぼ全員にいえることですので、全体をカバーしおくのがベターです。
①紫外線を避ける
紫外線(UV)は、体の健康に欠かせないものです。しかし、あまりに多くのUVを浴びると皮膚がん、シミ、シワなどの原因となります。
主要な方法として、日焼け止めを塗る、UPFの高い洋服を着る、日陰を歩くなどの対策でUVを避けることができます。
このような方法をとっても、屋外であればなんらかの形でばく露することになるため、できる限りの正しい対策を講じる必要があるでしょう。
UV対策が必要な人は、老若男女を問わず全ての人が対象になります。なぜなら、過度なばく露はデメリットがメリットを上回るためです。
②適度な運動を心がける
上述したように、運動は抗酸化能力を向上させ、酸化ストレスの影響を減らしてくれます。しかし、どのくらいが適切なのかは意見がわかれているのも事実です。
ここで、BMJに掲載された2016年のメタ分析を例にすると、「あらゆるエクササイズと5つの疾患リスクから用量反応関係」を調べたところ、最も大きな改善を示したのは、最大3,000〜4,000メッツ・分/週(50〜約66メッツ・時/週)であることがわかりました。
なので、ざっくりいえば『厚生労働省が推奨している量の2倍』を行う計算になります。
ですが、絶対リスクでは大きな差は出ない可能性がありますので、どんな人でも多めに運動をしてみると良いかもしれません。
③食生活に気を付ける
抗酸化で気をつけたいのが食生活です。酸化したものを食べるのは言語道断ですが、酸化ストレスのダメージを極限まで減らすためには抗酸化力の高い食べ物を摂取するのがマストですからね。
主な抗酸化物質は、ビタミンC・ビタミンE・グルタチオンがあり、近年ではフィトケミカルに注目が集まっています。ですが、基本的には厚生労働省が推奨する「日本人の食事摂取基準(2020年版)」を目安に食べていれば大きな問題は起きないと思われます。
食事に関していえば、活性酸素種と同じくらいAGEsにも気をつけたいところで、すべての人で理解しておくべきトピックでしょう。
厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2020年版) https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf
④十分な睡眠をとる
上記3つの項目と同じように、十分な睡眠も大事です。とはいえ、「睡眠不足」が酸化ストレスとなることが示されているため、適度に睡眠をとっていれば問題はありません。
しかし、「適度な睡眠」は人によりさまざまで明確なガイドラインがありません。
なぜなら、生まれ持った遺伝子の影響を強く受けたり、学業や仕事などのライフパターンに左右されたりと、一般化が難しいためです。
よって、厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針2014」を参考に考えてみると良いと思われます。
一方で、死亡率との相関も示されているので、多くの場合は6〜9時間の間になると思います。睡眠に関しても、すべての人で気をつけるべきポイントでしょう。
⑤禁煙
喫煙には活性酸素を爆増させる相互作用があります。つまり、酸化ストレスの大きな原因となります。
事実、禁煙3か月で酸化ストレスマーカーが有意に減少したことも報告されています。
喫煙は本人だけでなく、周囲の人に対する受動喫煙、喫煙後に衣服や指先などに付着した残留物質を吸うことで起こる3次喫煙も問題視されているほどなので、禁煙のメリットは大きいといえるでしょう。
特に、妊婦や乳幼児がいる家庭では気をつけておきたいところです。
まとめ

生活習慣が乱れて慢性化してしまうと、活性酸素が身体の抗酸化力を上回って酸化ストレスの原因となり得ます。
しかし、活性酸素がすべて悪いわけではなく、免疫機能や細胞伝達物質として働くため、うまく付き合っていく必要があります。
ひとことでまとめてしまうと、「一般的にいわれる健康的な生活がベスト!」になってしまうわけですが、そううまくもいきません。
できる限り、リカバリーをしてストレスケアも忘れずにやってくださいね。

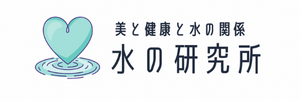



コメント